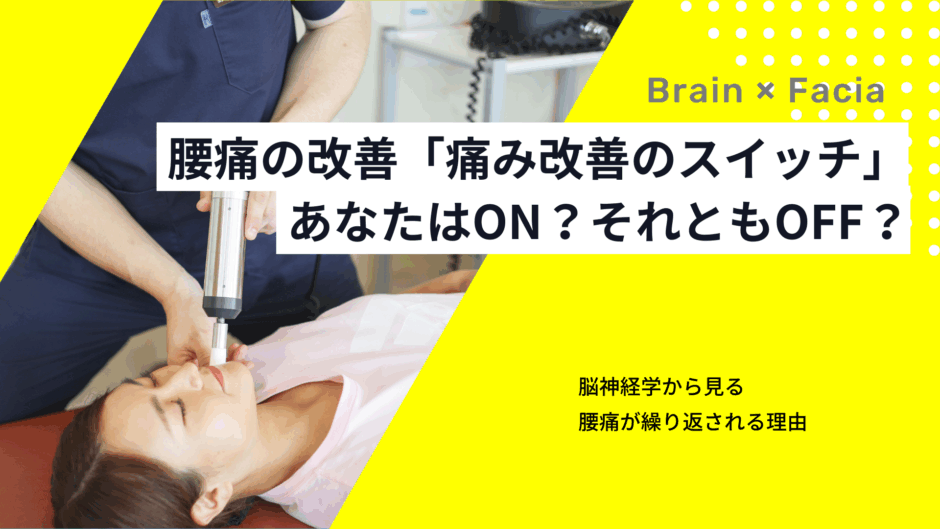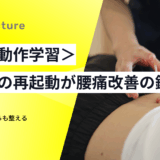こんにちは。てあつい整体院の佐伯です(柔道整復師・国家資格保有)。
当院には、
「病院では異常なし」
「湿布や薬は効かない」
「マッサージをしても、その場だけ」
といった、深刻な悩みを抱えた多くの患者様が来院されます。
実は、そのしつこい腰痛の本当の原因は、あなたが思っている場所とは違う「神経の疲れ」にあるのかもしれません。
今回はそのメカニズムを、専門家の視点から徹底的に解説していきます。
腰痛が続く…原因は、脳の機能!?
慢性腰痛の背景には、「動く意欲」と「痛みを抑える働き」を司る脳の機能(下降性疼痛抑制系)が深く関わっています。
その機能がうまく働かなくなると、痛みは長引き、改善しにくくなるのです。
身体の“やる気スイッチ”=側坐核(そくざかく)
側坐核は、脳の中心部にある「やる気・前向きな行動」を生み出す重要な場所。
● 側坐核の本来の役割
- やる気を生み出す
- 前向きな行動を起こす
- 動くことでスッキリ感を得る
- 運動によって痛みを抑える働きがある
特に注目すべきは…
側坐核が働くことで「痛みを落ち着ける機能が働く(下降性疼痛抑制系)」という点です。
● なぜ側坐核が働かなくなる?
- 痛くて動かない
- 「また痛くなるかも」という不安
これらが続くと、
脳にある「扁桃体」という部分が働いてしまいます。
そうすることで、側坐核は働くことができなくなるシステムがあるのです。
これは「気持ちの弱さ」ではなく、脳の活動である“生理学的な現象”です。
不安スイッチ=扁桃体(へんとうたい)
扁桃体は、危険を察知して身体を守るための“警報装置”のようなものです。
●本来の役割
- 危険を察知して身を守る
- 防御反応を起こす
- 痛みを「適切に」認識する
● なぜ扁桃体が暴走する?
- 「また痛くなるかも」という恐怖
- 過去の痛み経験の蓄積
- ネガティブな予測
- 長期的なストレス
これらが続くと、
- 扁桃体が敏感化(オーバー警報)
- 側坐核が働かなくなり、痛みを抑制する機能が働かない
- 小さな刺激でも痛みを強く感じる
- 動く前から身体が固まる
つまり、痛みを抑える装置が、逆に痛みを増幅する状態になるのです。
慢性腰痛ループが完成する
・側坐核(やる気スイッチ)が働かない
・扁桃体(不安スイッチ)が暴走
この2つがそろうと、人間が本来持っている「痛みを落ち着けるシステム(下降性疼痛抑制系)」が働かなくなります
- 痛みが怖い
- 動かない
- 身体が固まる
- さらに痛い
- もっと怖くなる
- もっと動けなくなる
この恐怖回避(フェアーアボイダンス)ループが慢性腰痛を長引かせる大きな原因になります。
まとめ:脳のスイッチを整えることが鍵
慢性腰痛は、
「身体が壊れているから治らない」とは限りません
脳のスイッチがうまく働いていないだけのことも多いのです。
- やる気スイッチ(側坐核)
- 不安スイッチ(扁桃体)
この2つを整えることが、
「本当に長引く腰痛」から抜け出す大きなカギとなります。
最後に
いかがでしたでしょうか?
てあつい整体院では、神経学や解剖学に基づいた施術を行っています。
不調の背景は単純ではなく、生活習慣や体質、脳神経・筋膜・骨格・ホルモンなどが複雑に関係しています。
だからこそ私たちは、評価 → 施術 → 再評価を重ね、リセット → 学習 → 定着のプロセスを大切にしています。
その積み重ねを通じて「心身の変化」を実感し、あなたらしい日常を取り戻していただけるようサポートいたします。
※効果や体感には個人差があり、必要に応じて医療機関の受診をご案内します。