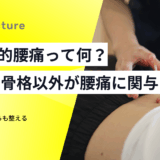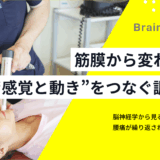こんにちは。てあつい整体院の佐伯です(柔道整復師・国家資格保有)。
当院には、
「デスクワークで午前中から腰が硬くなる」
「中腰作業で腰がズーンと重くなる」
「湿布や薬ではもう効かなくなってきた」
といった、深刻な悩みを抱えた多くの患者様が来院されます。
実は、そのしつこい腰痛の本当の原因は、あなたが思っている場所とは違う「神経の疲れ・前庭機能」にあるのかもしれません。
今回はそのメカニズムを、専門家の視点から徹底的に解説していきます。
前庭機能とは?——身体の“重力センサー”
前庭とは、耳の奥(内耳)にある三半規管と耳石器のことを指します。頭の動きや傾きを感知し、その情報を脳幹・小脳・視床・大脳皮質へと伝達します。
つまり、前庭は私たちの身体にとって「重力を感じ取るセンサー」であり、“脳へのインプットの入り口”のひとつです。
前庭と脳の連携とは?
前庭から送られた情報は前庭脊髄路(VSR)を通じて、首や体幹の筋肉に反射的に信号を送ります。これにより、
- 頭の位置をまっすぐ保つ
- 重心を中央に戻す
- 左右のバランスを微調整する
といった姿勢制御が、無意識のうちに行われています。
この反射が鈍くなると、重心バランスが崩れ、筋肉の一部が過緊張状態になりやすくなります。
前庭機能と腰痛の関係
前庭機能が低下すると、脳は姿勢を保つために必要以上の筋緊張を起こします。たとえば、
- 片側の背中の筋肉や腰の筋肉が硬くなる
- 骨盤が傾く
- 立ち姿勢・座っている姿勢での重心がずれる
これらが慢性的に続くと、腰の筋肉や関節に負担がかかり続け、「筋肉由来ではない腰痛」が生じます。
また、前庭の働きが乱れると脳内の「痛み認識システム(視床・島皮質)」にも影響し、痛みが強く感じられる状態に陥ることもあります。
視覚・体性感覚との“感覚統合”
前庭は、視覚・体性感覚と連携しながらバランスを保ちます。
この3つのバランスがズレると、脳は正しい姿勢制御を行えません。
- 眼球運動が不安定 → 脳幹入力の低下
- 足裏感覚の鈍化 → 重心のズレ
- 前庭情報の誤作動 → 代償的な筋緊張
結果として、「筋肉が常に頑張りすぎる状態」が続き、腰への負担が増していきます。
てあつい整体院のアプローチ
当院では、筋肉や骨格を整えるだけでなく、脳への感覚インプットの質を整えることを重視しています。
- 前庭刺激トレーニング:頭位変換や重心移動を用いた反射再教育
- 眼球運動トレーニング:サッカード・スムーズパースートによる脳幹活性化
- トムソンベッド矯正:骨盤・脊柱アライメントの再調整
- TNブレイン刺激:三叉神経を介した脳幹入力の改善
- 楽トレ(EMS):インナーマッスルの再教育と姿勢安定化
- ハイボルト療法:神経伝達・筋活動の最適化
「神経から変える整体」によって、脳の姿勢制御機能を再学習させ、再発しにくい身体づくりを目指します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
てあつい整体院では、神経学や解剖学に基づいた施術を行っています。
不調の背景は単純ではなく、生活習慣や体質、脳神経・筋膜・骨格・ホルモンなどが複雑に関係しています。
だからこそ私たちは、評価 → 施術 → 再評価を重ね、リセット → 学習 → 定着のプロセスを大切にしています。
その積み重ねを通じて「心身の変化」を実感し、あなたらしい日常を取り戻していただけるようサポートいたします。
※効果や体感には個人差があり、必要に応じて医療機関の受診をご案内します。