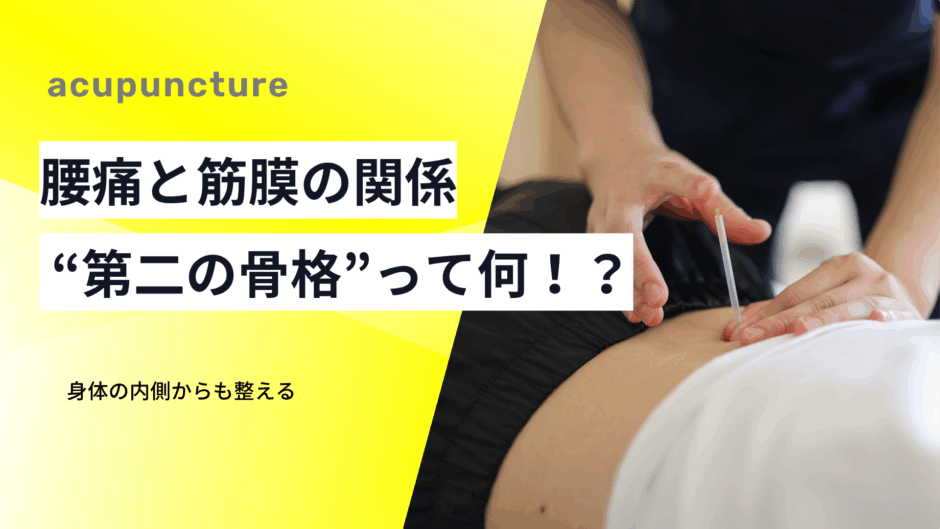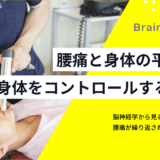こんにちは。てあつい整体院の佐伯です(柔道整復師・国家資格保有)。
「腰が痛くて仕事に影響が…」「マッサージしてもすぐ戻る」「姿勢を整えても腰が重い」
といった、深刻な悩みを抱えた多くの患者様が来院されます。
実は、そのしつこい腰痛の本当の原因は、あなたが思っている場所とは違う「筋膜」にあるのかもしれません。
今回はそのメカニズムを、専門家の視点から徹底的に解説していきます。
筋膜とは?──全身を包む“ボディースーツ”
筋膜は、コラーゲンなどからなる結合組織の膜で、筋肉・骨・神経・内臓までを立体的に包み込み、 体を一枚のネットワークにまとめます。イメージは“全身を覆うボディースーツ”。このネットワークが、姿勢の土台になり、 離れた場所同士の動きや力も伝え合います(例:足の硬さが腰の動きに影響)。
浅筋膜・深筋膜って?
筋膜にも、深い所にある筋膜、浅いところの筋膜に分かれます。
- 浅筋膜:皮膚のすぐ下の層。体温調節やリンパ・静脈の流れとも関係します。
- 深筋膜:筋肉の上を覆い、筋群どうしを区画化。力の伝達や姿勢・動きの協調に関わります。
なぜ筋膜が硬いと腰が痛くなる?
本来、筋肉と筋膜は“フィルム同士が滑るように”スムーズに動きます。ところが、長時間同じ姿勢・過去のケガ・使いすぎ・不動 などで筋膜がよじれたりくっついたりすると、“滑り(滑走性)”が悪くなり、動きがぎこちなくなります。さらに腰の周りだけでなく、足や背中など 離れた場所の張りや違和感にもつながります。
キーワードは「ヒアルロン酸」
筋膜どうしが滑るための“潤滑オイル”の役目をするのがヒアルロン酸。
ケガや炎症、動かさない期間、使いすぎが続くと、ヒアルロン酸が濃く固まりやすくなり、 ねばつき(粘性)が上がって滑りが悪くなります。結果、動作時の痛みや重だるさ、動きにくさを招きやすくなる。
これが慢性腰痛に絡む大きなメカニズムです。
筋膜には、「身体のセンサー」がついています
筋膜の中には、動き・圧・振動などを感じ取る“センサー”がついています(自由神経終末・ルフィニ小体・パチニ小体など)。
例えるなら、あなたの体の中に張りめぐらされた感知センサー。筋膜が硬いとセンサーが過敏になって痛み信号が増えたり、 逆ににぶくなって体の使い方(姿勢やバランス)が乱れたりします。
筋膜を整えると、このセンサーが落ち着いて「痛みを感じにくく、動きやすい」状態に近づきます。
てあつい整体院のアプローチ──筋膜×神経×歪みを同時に整える
① 筋膜マニピュレーション
筋膜のねじれ・癒着を見極め、滑走性を回復させる徒手アプローチです。
目標は、ヒアルロン酸の偏りを整え、筋膜の“滑り”を取り戻すこと。即時的に可動域や痛みの変化が出やすく、 日常動作(立ち上がり・家事・歩行)も軽くなる方が多いです。
② 神経ストレッチ(滑走性の回復)
神経も“膜のトンネル”を滑る構造。筋膜だけでなく神経の滑走も促すことで、しびれ・重だるさの軽減を狙います。 筋膜と神経は同じネットワーク上の問題としてセットで整えると効果的です。
③ 姿勢・歪みの矯正
骨盤・背骨の配列が整うと、筋膜への負担が減り“再び硬くなる”のを予防しやすくなります。
加えて、胸郭・横隔膜の働きを高める呼吸アプローチも行い、体内の環境(pHや温度・循環)を整えて、筋膜が柔らかさを保ちやすい状態へ導きます。
安全面について
発熱・広範な炎症・血栓症・皮膚病変など一部のケースでは、徒手刺激に配慮が必要です。該当の可能性がある方は、施術前に必ずご相談ください。
まとめ
筋膜は全身をつなぐ第二の骨格。滑り(滑走性)が落ちると、腰痛や張り、可動域の低下が長引きやすくなります。
てあつい整体院では、神経学や解剖学に基づいた施術を行っています。
不調の背景は単純ではなく、生活習慣や体質、脳神経・筋膜・骨格・ホルモンなどが複雑に関係しています。
だからこそ私たちは、評価 → 施術 → 再評価を重ね、リセット → 学習 → 定着のプロセスを大切にしています。
その積み重ねを通じて「心身の変化」を実感し、あなたらしい日常を取り戻していただけるようサポートいたします。
※効果や体感には個人差があり、必要に応じて医療機関の受診をご案内します。