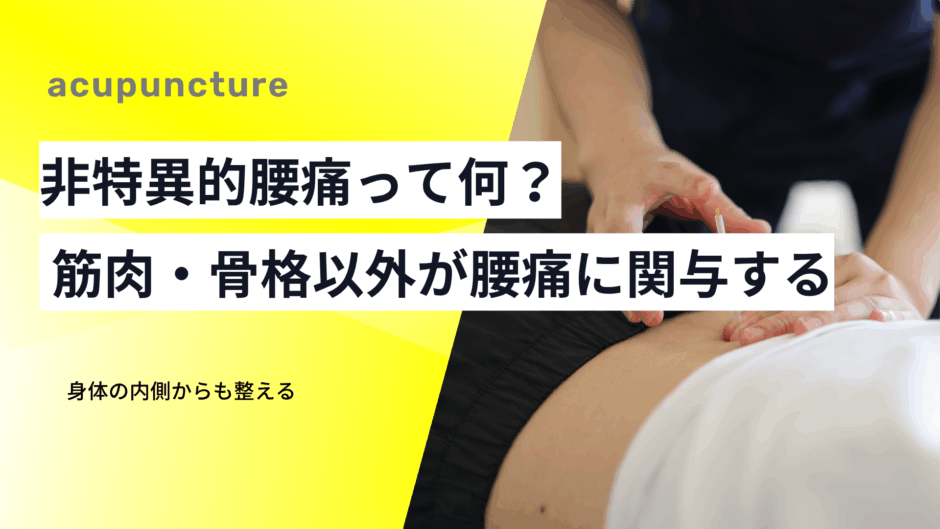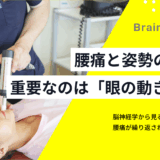こんにちは。
てあつい整体院の佐伯です(柔道整復師・国家資格保有)。
「病院でレントゲンを撮っても異常がない」「MRIでも原因がはっきりしない」「湿布や薬ではもう効かなくなってきた」
といった、深刻な悩みを抱えた多くの患者様が来院されます。
実は、そのしつこい腰痛の本当の原因は、あなたが思っている場所とは違う「神経の疲れ」にあるのかもしれません。
今回はそのメカニズムを、専門家の視点から徹底的に解説していきます。
腰痛の約85%は“原因が特定できない”?
多くの腰痛患者(特に一般の整形外科・クリニック受診者)では、レントゲンやMRIなどの画像検査、既往歴や理学検査を行っても「明らかな原因」が見つからないケースが多くあります。
このような腰痛は「非特異的腰痛(non-specific low back pain)」と呼ばれ、国際的には全体の約85%を占めると報告されています。
ただし、これはあくまで「原因がまったく存在しない」という意味ではなく、画像や検査で明確に説明できないということです。
実際には、より詳細な評価を行うことで、痛みの発生源をある程度特定できるケースもあります。
つまり、「腰痛=原因不明」と考えるのではなく、“原因が一つではない”ことを前提に、多角的に考える必要があります。
筋肉・骨格以外の要因も無視できない
一般的に、腰痛といえば「筋肉の張り」や「骨格の歪み」「椎間板の変性」など、構造的な異常が原因と考えられがちです。
しかし、近年の研究では筋肉や骨格以外の要因が痛みの発生・慢性化に大きく関与していることが分かってきました。
① 神経・感覚などの脳神経の機能(中枢感作)
一度痛みを経験すると、脳や脊髄の神経回路が“痛みを感じやすくなる状態”に変化することがあります。
これを中枢感作(central sensitization)と呼び、構造的な異常が見当たらなくても痛みが続く原因になることがあります。
また、脳神経系の機能低下(脳幹・小脳・大脳皮質のネットワーク異常)が、痛みや姿勢制御に関わるという報告も増えています。
② 心理・社会的ストレス・感情の影響
精神的ストレス、不安、うつ傾向、職場環境や人間関係などの心理社会的要因も、腰痛の発症や慢性化に関与します。
労働安全衛生総合研究所の研究でも、こうしたストレス要因が痛みを長引かせるリスクとして報告されており、労働衛生の分野でも重要なテーマになっています。
心と体は密接につながっており、ストレスで筋緊張が高まることや、自律神経の乱れによって血流や代謝が低下することも、痛みを悪化させる要因となります。
③ 姿勢・動作・クセ・生活習慣との相互作用
長時間のデスクワークやスマートフォン操作、猫背姿勢、体幹筋力の低下、肥満などの生活習慣も、腰への負担を増やす大きな要素です。
これらは単独で問題を起こすというよりも、神経・筋肉・心理的要因と複合的に作用し、慢性腰痛を形成していきます。
④ 栄養・人間関係
近年では、栄養状態(ビタミン・ミネラル不足)や社会的孤立、人間関係のストレスなども体の炎症・神経機能に影響することが分かっています。
改善には、多角的なアプローチが必要
腰痛の本当の原因は、筋肉や骨格だけでなく、神経・心理・生活習慣・脳機能など多くの要素が絡み合っている可能性があります。
そのため、改善には「一方向の治療」ではなく、以下のような多面的アプローチが必要です。
- 神経・筋肉・骨格のバランスを整える施術
- 脳神経機能を高めるトレーニングや刺激
- 姿勢・動作のクセを修正する運動療法
- ストレスマネジメント・睡眠・栄養の見直し
痛みの背景は一人ひとり異なります。
そのため、私たちは「身体の状態」「神経の反応」「生活習慣」のすべてを評価し、あなたに合った根本的な施術プランを提案しています。
まとめ
「腰痛の85%は原因不明」と言われる背景には、検査で明確に映らない“見えない要因”が多く存在します。 筋肉や骨格だけでなく、神経・心理・生活習慣・脳機能などを含めた総合的な視点こそ、腰痛改善への第一歩です。
てあつい整体院では、神経学や解剖学に基づいた施術を行っています。
不調の背景は単純ではなく、生活習慣や体質、脳神経・筋膜・骨格・ホルモンなどが複雑に関係しています。
だからこそ私たちは、評価 → 施術 → 再評価を重ね、リセット → 学習 → 定着のプロセスを大切にしています。
その積み重ねを通じて「心身の変化」を実感し、あなたらしい日常を取り戻していただけるようサポートいたします。
※効果や体感には個人差があり、必要に応じて医療機関の受診をご案内します。
参考文献:Maher C et al., 2017; Hartvigsen J et al., 2018; Woolf CJ, 2011; Linton SJ, 2011; Baliki MN, 2015; 吉村一朗ほか, 医学書院, 2024 ほか。